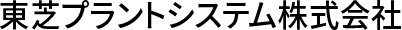社会インフラ事業部
社会インフラフィールドサービス部 交通グループ
自分の携わった仕事が
“目に見えて”人の役に立つ。
それが、醍醐味ですね。
試験・試運転調整担当 #07
2012年入社
大学院卒(専攻:電気情報工学)
自分が携わった装置が実際に機能し、動き出す面白さ
私は今、社会インフラ事業部の社会インフラフィールドサービス部 交通グループで、鉄道の車両制御の中核となるデジタル伝送装置のシステム検証を担当しています。
システム検証には2段階ありまして、1つは工場内で他の機器をシミュレーションして装置単体で試験を行う「工場試験」です。
そして、もう1つが客先ですべての機器を実際につなげて動作確認を行う「現地調整」です。
私が、現地調整を初めて任されたのが、入社4年目の2015年 11月でした。それまで工場試験の経験は積んでいましたが、初めての現地……しかも、海外(タイ)ということもあり、とても緊張した日々を過ごしました。しかし、目の前で自分の携わった電車が動き出した時は、ものすごい充実感がありました。
仕事の結果が“目に見える”社会インフラ事業部を志望
私が入社時に希望したのは社会インフラ事業部という大枠だけで、細かな部署までは考えていませんでした。上下水道でも、空港でも、人々の生活を支えるインフラに携わることが出来れば良いと思っていました。
一番魅力を感じていたのは、どの部署が担う仕事でも、その結果が「一般の人々の目にも見えている」ことです。やりがいがありそうだと思いました。
そして、鉄道関連の仕事に配属された時は、「設計かな?」と思っていましたが、「現地調整」でした。最初は、「それってどういう仕事だろう?」と思いましたね。会社に入って初めて、そういう仕事があると知りましたから。
最初は分からないことだらけで、仕様書や図面とにらめっこしながら、時に先輩方に質問をしてメモを取る毎日でした。

重い責任を伴う仕事だからこそ、やりがいも大きい
仕事は忙しいし、残業もある程度は生じます。でも、忙しいことは良いことだと思っています。「上司も、自分に期待して大きな案件を任せてくれているのだ」と考えると、とてもありがたいですね。
最初のうちは、保安装置やモニタ装置という情報系の装置にしか、携わっていなかったのですが、実際に車両を制御する主回路や補助電源、空調など車両全体の装置に携わるようになって、電車全体を把握できるようなりました。
やはり、実際にモノが動いて、人の役に立つというのは、面白いですよ。
大勢の人々が利用する交通機関の制御ですから、非常に責任は重いです。でも、だからこそ、エンジニアとしてのやりがいや成長を実感できるのだと思います。
学生へのメッセージ
私が就職活動を行った際に、一番重要視したのが実は「離職率の低さ」なんです。いろんな情報がありますが、数字に裏付けられた情報は嘘をつきませんし、「離職率が低い」ということは、「働きやすい」ということにもつながるのだろうと思いました。
実際、入社してみたら、部内の雰囲気もいいですし、離職率は今も変わらずに低いと聞いています。この選び方も間違っていなかったと思います。